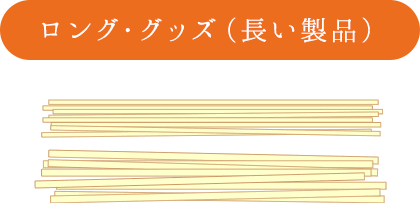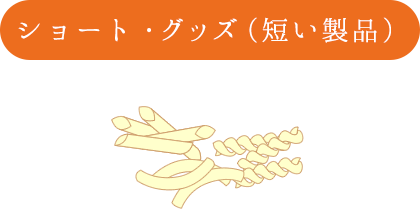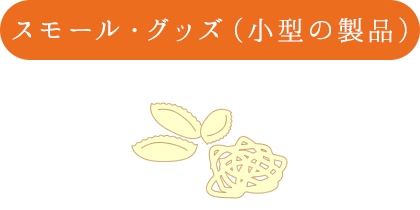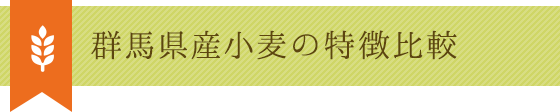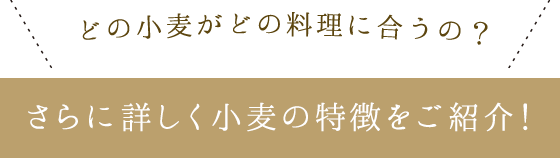めん処上州
古く上毛野(かみのつけ)、上野(こうずけ)の国名が与えられていたことから、上州と呼ばれるようになった群馬県。本州のほぼ中心、関東平野の北に位置する上州群馬は、上毛三山と呼ばれる赤城山、棒名山、妙義山をはじめ谷川岳、尾瀬湿地、吾妻峡など緑豊かな山々と、利根川をはじめとする豊富な水流による、自然に恵まれた地として知られています。赤城山の空っ風やかか天下など、上州独自の風土や気質を表す言葉もおなじみとなっています。
めん処上州の粉食文化
昔からめん処として知られている上州は、乾燥した冬の気候・日照時間の長さ、肥沃な関東ローム層の土壌、利根水系の豊かな伏流水など、小麦の生産に必要な条件が満たされていました。うどん、そばは日常食としても行事食としても主流ですが、「お切り込み」、「焼きもち」、「焼きまんじゅう」、「香煎・麦落雁」など独自の粉食文化があったようです。
うどんHistory

うどんの起源
うどんの起源については、今のところ定説はありませんが、室町時代の切り麦がうどんの元祖ではないかと考えられています。切り麦とは、小麦粉を練った塊を麺棒で薄く延ばし、それを包丁で細長く切る麺のことと解釈されています。それによると、切り麦を茹でて熱いうちに蒸籠に盛って食べるのがあつむぎ(熱麦)、茹でてから冷やし洗い、大きな木の葉やざるに盛って食べるものがひやむぎ(冷麦)、そして熱い汁に入れて食べるものがうどん(饂飩・うんどん)とされています。
パスタの今と昔

17世紀、トマトとの出会いでうまれたパスタ
「冒険家マルコ・ポーロが中国から麺を持ち帰ったのがスパゲッティのはじまり」とか。「いやいやイタリアにはそれ以前からマカロニがあった」とか。イタリアでのパスタの起源に関する説はいろいろありますが、とにかく、現代のようにソースとからめて食べるパスタ料理がイタリアに普及しはじめたのは、17世紀のトマトとの出会いがきっかけでした。(※)そして、17世紀半ばをすぎるころから、パスタ料理はイタリアから世界に広がっていきました。
※新大陸からイタリアにトマトが上陸したのは16世紀ですが、パスタ料理に使われる食用トマトが出現したのは17世紀です。

パスタが日本上陸!
日本にパスタが伝わったのは明治28年(1895年)。新橋のレストランのコックさんがイタリアから持ち帰ったのが最初と言われています。その後、昭和初期から少しずつ国産化が始められましたが、まだまだめずらしいもので、ホテルや一流レストランでしか口にすることができませんでした。一般化したのは、イタリアから全自動式パスタ製造機が輸入され大量生産されるようになった昭和30年代以降のこと。そのころ国産パスタは、日本人の味覚や食感の好みに合わせて、複数の小麦粉をブレンドしてつくられていました。やがて海外旅行に出かける人が増えたり、イタリアンレストランのブームなどで日本人のパスタの好みも変わり、昭和61年(1986年)頃からデュラム・セモリナ100%の国産パスタが家庭でも使われるようになりました。そしていまやパスタは、私たち日本人の家庭料理としても楽しまれ愛される食材になったのです。
(社)日本パスタ協会 「パスタ、めしませ。」より
群馬県の小麦事情
- 北海道
- 668,400
- 福岡
- 67,800
- 佐賀
- 46,100
- 愛知
- 31,600
- 群馬
- 23,300
- その他
- 187,800
単位:トン 参照元:農林水産省「農林水産統計 令和元年産4麦の収穫量」
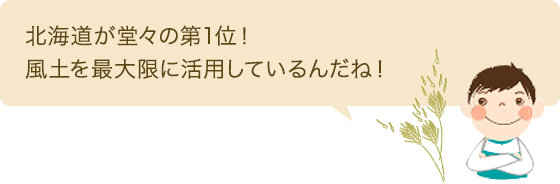
群馬の小麦は秋蒔き小麦で、11月上旬に種を蒔き、6月上旬から下旬に収穫されます。冬期の空っ風に耐え、太陽の光を存分に浴びて成長し、5月中旬頃には小麦畑は緑の絨毯のように、収穫時期には黄金色の絨毯に変わります。群馬の小麦が高品質(粘りが強く、もちもちしたうどんになります。)なのは冬期の空っ風と日射量(冬期の日射量は日本一)のおかげかもしれません。
- さとのそら
- 鮮やかなクリーム色、粘りとコシのバランスに優れためん用小麦、ソフトでふっくら感のあるうどんになります。
- つるぴかり
- 爽やかな乳白色、強い粘りのもち系めん用小麦、モッチモチのうどんになります。
- ダブル8号
- 高タンパク小麦、中華麺やそうめんなどに適しています。しなやかで弾力の強いめんになります。
- きぬの波
- 明るいクリーム色、粘りとコシのめん用小麦、なめらかで弾力のあるうどんになります。
参照元:群馬県製麺工業協同組合
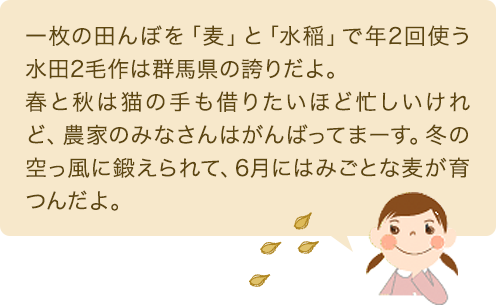
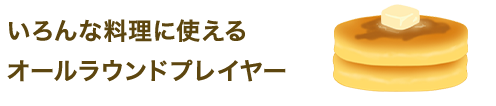
-

「さとのそら」は、やきそば、うどん、お好み焼き、ホットケーキ、パウンド・ケーキ、かりんとうなど幅広い小麦料理に適してるんだって。
-

さすが、オールラウンドプレーヤーだね!

-

「きぬの波」「つるぴかり」は、うどんやおきりこみなど群馬県の郷土料理ファンの要望に応えて「めん」専用に開発された小麦なんだって。
-

今では、群馬県内、県外でひろく愛用されているんだって。
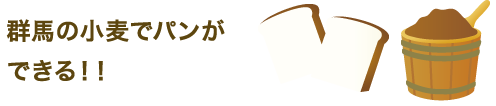
-

「ダブル8号(W8)」は、たんぱく質含有量が高いため、パンが焼け、みそやしょうゆの原料に使われる小麦なんだよ。
-

育種番号W8号が「末広がりで縁起がいい。」とそのまま品種名になったんだって。
参照元:JA全農ぐんま